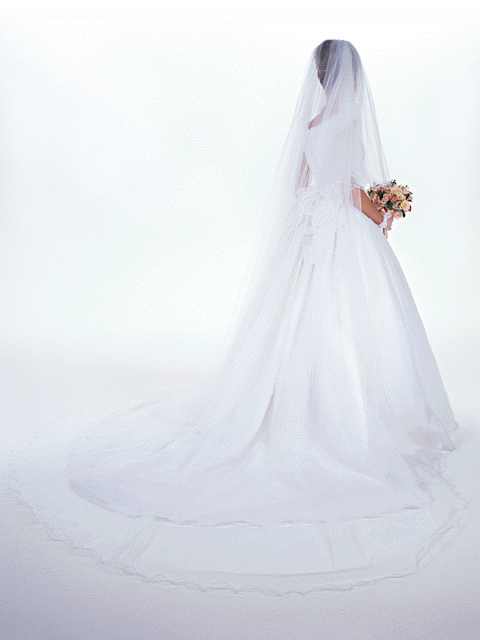「お主なら、その者を倒せる、と申すか」 「ははっ!仰せのままに」 ラインハルトは顔を伏せたまま答えた。 「ふむ…しかし儂の元に来た者は皆、そう言っておった。…そして帰ってこなんだ」 「恐れながら陛下、それらの者どもは裏切り者どもである、と思われまする」 「ほう、裏切り者とな」 「はは」 「何故そのように思う」 「こちらに参った者どもが、陛下より賜りました武具、防具等々を持ち、敵前逃亡したものでは無いか、と」 「ふむ、まあよい。期待しておるぞ」 「ははっ!」
息を切らしているラインハルト。 「ふう、なかなか…」 対する相手も身体のあちこちに傷を負っている。 「流石に…すばしこさ…だけは…かなりのものだな」 「おたくも…騎士の割には、はしっこいね」 「いい加減名を名乗るがいい!」 「俺らはあんたがたと違って名誉なんてクソ食らえさ…じゃあ、あんたがたに当てつけて騎士殺し(ナイト・キラー)とでも呼んでくれや」 なんの変哲も無い男だった。こいつが本当に国そのものに脅迫をかける程の悪党だと言うのか? ラインハルトはこの男を見下していた。どこから盗んで着たのか、奴は王侯貴族とまでは言わないが、身分不相応な服を着ていた。 全く理解出来ない。革命を起こして貴族に成り代わろうとでも言うのか? ここは奴の庭である。 小高い丘に自分の居城を構えて、山賊の頭領を気取っている下司な男だ。こいつが国に対して脅迫状を送り続けてきた。曰く、大金を寄越さねば呪いによって災いをなす、と。 当然、王は無視を決め込んでいた。しかし、飼い猫が病死したり、雨が降り止まなかったり、杖が蛇に変わったり、と些細なことではあるが、その脅迫状に書かれている「予言」はことごとく的中したのだ。 遂に王は重い腰を上げ、要求は飲めないが、宮廷お抱えの予言者として召し抱える用意がある、との書状を持った使いを出すも、その使いが帰ることはなかった。 際限なく肥大するその要求に、遂に暗殺者が差し向けられるも、暗殺はことごとく失敗。名うての冒険者、傭兵、騎士が討伐に向かうも、やはり帰ってくる者は一人として無かったのである。 こいつにどうやって負けるというのか? ラインハルトは幅広の剣(ブロード・ソード)を構えた。 逃げ回るばかりで何の反撃もしてこないではないか。 「騎士(ナイト)さんよお、あんたは運がいい」 「とおりゃああ!」 切っ先が男をかすめる。しかし、致命傷には至らない。 「今日は連中の機嫌がいまいち良くねえらしいんだ」 「その「連中」ってのは悪魔のことか」 「察しがいいじゃねえか」 「この邪教徒があ!」 やはり逃げ回る男。 庭に積み上げて合った箱に衝突するラインハルト。中身がぶちまけられる。中からはきらびやかなドレスが出てくる。 「何と!これはご婦人方のお召し物では無いか!」 「ああ、そうだぜ」 「こんなものを盗んでなんとする」 「俺は最近女の服に興味があってな」 「この変態めがあ!斬り捨ててくれるわあ!」 再び距離をとる男。 「騎士さんよお、勘違いしちゃいけねえなあ」 「何を!この下司があ」 この斬撃もかわす男。 「あんただってそうだろ?俺が女の服に興味があるって言ったのは、もっぱら脱がすことについてさ」 「黙れ黙れ!汚らわしい!」 「あと、最近は「着せる」こともな」 その一言を言い終わらないうちに気合いと共に斬りかかるラインハルト。 もんどり打ってかわすも、ラインハルトの腕には確かな手応えが残る。 地面に点々と血痕が走る。 腕を押さえている男。これまでにない出血が認められている。 「ふ、どんな呪術が使えるのか知らんが、悪行もここまでだな。覚悟するがいい!」 が、男の表情は不敵な笑みへと変わっていった。 「残念だがそれはこっちの台詞だね。どうやら間に合ったようだ」 「やかましいわ!」 「誤解されるといけねえから先に言っとくわ」 男の態度が一変する。それまで逃げ回るのみだったものが、奇妙な「構え」を取り始めたのだ。 「俺がこの術を覚えたのは遙かにガキの頃さ」 こちらに向かって間合いを詰めてくる。ラインハルトは用心深く身構える。 「こいつは強力だったな」 脂汗が眉間を流れ落ちる。落ち着け、こいつは瀕死だ。武器も持たずにどうしてこの私に勝てようぞ。 「最初のうちは意味が分からなかったよ。どうして相手が弱くなるのかがな」 次の呼吸に合わせて打ち込んでやる…。 「だが、今ははっきりと分かる」 「きえええー!」 動きが違う!これまでとは比較にならない素早さで懐に潜り込まれた。 しまった!しかし男はガントレット(籠手)の上からぽん、と両腕を触っただけで同じスピードで駆け抜けて行った。 「まずは攻撃力を奪う…。悪いな」 その瞬間、それまで手の一部てあるかの様に振り回していた剣が、鉛の様に重くなった。とても支えきれずに地面に落ちる。 「…!き、貴様あ!何か術を使ったな!卑怯者め!」 「卑怯だあ?これまでさんざんそのでっかい剣を力任せに振り回してたのはどこの誰なんだよ。こっちにはこっちの戦い方ってものがあるんだ」 何故だ?腕に力が入らない…しかも、何だこれは?…籠手がゆるゆるになっているではないか…。しかもプレートメイルまで…ええい! 理由は分からないが、ゆるゆるになってしまった籠手をむしり取る。 ラインハルトは信じられないものを見た。 巨木の幹の様に鍛え上げられた強靱な腕はそこには無かった。少し力をこめれば折れてしまいそうなか細い腕があったのだ。 「な、なんだこれは…」 次の瞬間、また男が突っ込んでくる。 「おらおら!戦闘中によそ見してんじゃねえよ!」 しかし、またも男は不可解な行動を取った。顔面に強烈な加檄を加えることも可能であろうに、軽く頬にぽんと触っただけで駆け抜けてしまったのだ。 が、次の瞬間、目の前を無数の黒い線が覆った。 「うわっ!」 信じられなかった。その叫び声はとても自分のものとは思えなかった。細く、高い、可愛らしい声だったのだ。 「ほうほうほう、…これはまた…」 その美しい手で視界を遮る髪を必至にかき分けるラインハルト。 「止めろ…止めるんだ!」 「ん?それは俺に言ってんのか?」 不敵な笑みを止めない男。 「じゃあ、そろそろ本番行くぜえ!」 「おおおおおおおおおあああ!」 ラインハルトは思いきり持てる力を振り絞った。そのか細い、白魚のような手で鉛の様に重い剣をかつぎあげ、突進してくる男を迎撃したのだ。 「うおっ!」 まともに食らったのか、もんどりうって倒れこむ男。 が、しかしこれが限界だった。剣を取り落とすラインハルト。痺れてまともに動かすことすら出来ない。それどころか、今度は全身に装着した鎧が数倍の重さになって襲いかかってきたのだ。 「なかなか根性あるじゃねえか…」 額を切っている男。ラインハルトはそれどころでは無かった。 身体が…身体が小さくなっている! プレートメイルの首の部分が唇のところまで来ているのだ。しかもそれだけではない。鎧の中にも変化が起こっていた。 「こ、これは…」 まるで女のように胸が膨らんで内側から鎧を圧迫しているのだ。むき出しにされたそれが、中に着込んでいる鎖かたびらにごりごりと接触し、先端に痛みが走る。 「へ、悪いな」 最早男はフットワークすら使わなかった。全く身の丈にあっていない巨大で鈍重な鎧に縛り付けられ、動けない。 その胸の部分に強烈な券撃が加えられる。 「ぐわっ!」 下半身にぽん、と触る男。それで決定的だった。 か弱い足腰では支えきれず、崩れ落ちる。 「どうだい今の気分は?」 胸が猛烈に痛む。それどころではない。 「戦闘時に男には股間が弱点だが、女の場合は胸がそれにあたる」 おびえるような目つきのラインハルト…だった女性。 「ほんの少しでも触れればあとは思い切り胸をぶん殴ればいい。俺はそうやってどんな相手との格闘でも勝ってきた」 慣れた手つきで鎧を脱がせていく男。豊かな乳房が鎖かたびらごしに空気にさらされる。 「や、やめろ…」 「嫌だね。今じゃこれが楽しみなんだから」 動きが無くなった相手を催眠状態にすることなどこの男には朝飯前なのだろう。身体が動かない。しかし、感覚だけは全て残っている。あっと言う間に一糸纏わぬ生まれたままの姿にされてしまう。 身体が動かない。遠くから何か、大きな物を持ってくる男。何だ?あれは何だ?拷問道具なのか? 「お前、今俺が拷問道具を持ってくると思っただろう。当たりだ。…ある意味な」 それはさっきの美しいドレスだった。 見開かれるラインハルトの目。 「楽しもうぜ。騎士殿…いや…お姫さま」
ラインハルトもまた、凱旋することはなかった。
|